Google AIモード日本開始:実践ガイド
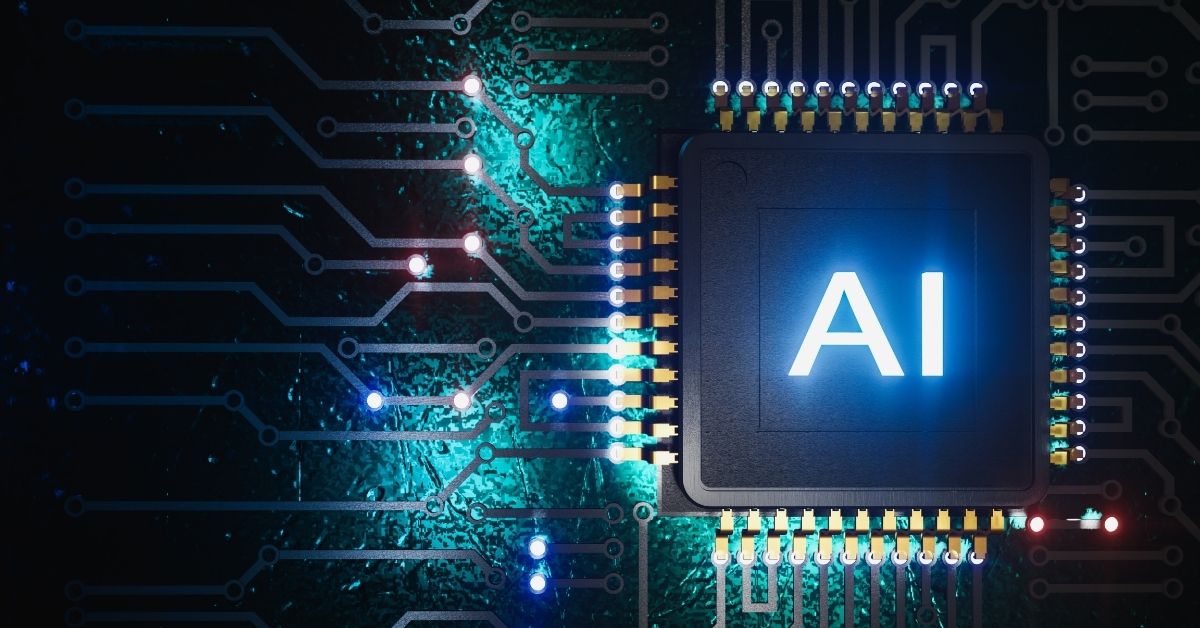
はじめに
2025年9月9日、Googleは日本向けに「AIモード」の提供を開始しました。AIモードは従来の検索体験を大きく変える機能で、Geminiのカスタム版(報道ではGemini 2.5ベース)とクエリファンアウト技術を組み合わせ、1回の検索で複雑な問いに包括的に応答します。PC・モバイルの検索結果頁に専用タブとして表示され、テキストだけでなく音声や画像入力に対応するマルチモーダル機能を備えています。
本記事は、企業やマーケター、SEO担当者向けにAIモードの本質、ビジネスインパクト、即実行できるAIO(AI Optimization)施策を専門家の視点で解説します。導入で懸念される"ゼロクリック"問題や引用の扱い、実際にAIモードでの検索結果に引用されるための技術・コンテンツ戦略まで、事例と手順を交えて実務に直結する形でまとめます。
基礎・概念理解
AIモードとは何か、なぜ重要なのかをまず整理します。従来の検索はリンクリストを提示してユーザーがサイトを訪問するフローでしたが、AIモードは検索画面内で高度な要約や推奨、解決策を提示することで"その場解決"を促します。技術的には大型言語モデル(LLM)に基づく生成と、検索インデックスの情報を組み合わせるハイブリッド方式が中心です。
この変化が意味するのは指標の転換です。クリック数中心のKPIから「提供価値」「引用される信頼性」「ユーザー満足度」へと評価項目がシフトします。Googleの報道(複数メディアによる発表や9月9日付の導入情報)によれば、AIモードは1回の検索で長い複雑な質問へ応答可能で、音声・画像入力にも対応するマルチモーダル能力を備えています。これにより、検索体験の多様化が進みます。
AIモードのコア技術要素を整理します。
- LLM(大型言語モデル): 文脈理解と自然な生成を担う。Gemini 2.5のカスタム版が日本語対応で利用されている点が報告されています。
- クエリファンアウト: 単一クエリを多数のサブクエリに分岐させ、各ソースから得られた情報を統合して最適な回答を作成する技術。
- マルチモーダル処理: テキスト・音声・画像を統合して理解することで、より具体的なユーザー要求に応える。
これらは、従来の検索アルゴリズムとは異なる最適化要件を企業・サイト運営者に要求します。次節でそれらの実務的示唆を深掘りします。
LLMと検索の融合
LLMと検索の連携は、情報源の信頼性検証と要約の品質が鍵です。LLM単体は生成過程で確証が弱い場合があるため、検索インデックスやファクトチェックモジュールでの裏取りが必須です。GoogleのAIモードは内部的にクエリファンアウトで複数ソースを参照し、引用情報を提示する設計が報じられています。これにより回答の根拠提示が改善され、ユーザーが出典にアクセスできる形を保とうとしています。
企業は自社コンテンツがAIの"引用候補"になるよう、構造化データや明確な引用可能テキスト、信頼できるメタ情報を整備する必要があります。具体的にはFAQ形式、要約文の冒頭、日付・著者情報の明示、一次ソースへのリンク強化が有効です。
マルチモーダル対応の基礎
AIモードはテキストに加え画像や音声入力を受け付け、画像認識や音声の言語変換を経て回答を生成します。例えば商品画像をアップロードして類似商品の比較・説明を求めるケースや、現場でスマホ撮影した写真をもとにトラブル診断をするケースが想定されます。これに対応するため、企業は画像のaltテキスト、図表の説明文、音声コンテンツの文字起こし(トランスクリプト)を提供することで、AIモードに利用されやすい資産を増やせます。
マルチモーダル最適化は、画像の品質やメタデータ、動画内のクローズドキャプション、音声ファイルの明確なトランスクリプションなどの整備が中心です。これらはAIが情報を正確に引用・要約する上での重要なプレ条件になります。
実践・応用
ここでは企業やサイト運営者がAIモード到来に備えて直ちに取るべき具体的アクションを提示します。ポイントは「引用されること」を目的化すること、そしてAIが好む形で情報を構造化することです。以下は実務で即実行できる優先順位付きチェックリストです。
- 構造化データとスキーマの実装(FAQ、HowTo、Product、News)
- 記事冒頭に要約(60-120字)を入れる習慣化
- 出典明示と日時情報の徹底
- 画像・動画のメタデータ(alt、caption、transcript)整備
- 定期的なコンテンツ更新ログの公開と更新日付の明示
これらはAIが信頼性の高いソースを選ぶ際に重要なシグナルとなります。特にFAQや短く簡潔な要約はAIモードにそのまま引用されやすく、"ゼロクリック"傾向の中でもブランド認知や問い合わせ誘導に寄与します。
AIO(AI Optimization)の具体手順
AIOとは、AI検索エンジンでの可視化を最大化するための最適化手法です。実装手順を示します。
手順1: 重要ページの優先リスト化。トラフィック、CV、ブランド影響の観点で上位30ページを選定。 手順2: 各ページに"ピンポイント要約"を作成(60〜120字)。AIは短い要約をそのまま提示することがあるため、FAQや冒頭文を充実させる。 手順3: 構造化データ(JSON-LD)を導入。FAQPage、HowTo、Article、Productなどを正確にマークアップする。 手順4: 出典と信頼性シグナルの明示。著者、所属、一次データへのリンク、更新履歴を明記。 手順5: 画像・音声のメタデータ整備。alt、caption、transcriptを必ず埋める。 手順6: モニタリングと改善。Search Console、GA4、専用のAI表示トラッキングでAIモード経由の指標を分離して観測する。
これらを継続的に実行することがAIモードにおける長期的な可視化に直結します。
コンテンツ設計と品質管理
AIモードは"短く、根拠があり、構造化された情報"を好みます。従って、コンテンツ制作プロセスの再設計が必要です。編集ガイドラインには以下を含めてください。
- 結論ファーストの要約(導入部に必ず掲載)
- 参照元の明示と一次データへのリンクを基本ルール化
- セクションごとに見出しと要点を箇条書きで用意
- FAQ化可能な問いを記事末に配置し、構造化データを付与
また、品質管理として事実確認プロセス、日付管理、専門家のバイライン(著者情報)を徹底してください。AIが引用する際、出典の信頼度が低いと表示順位に影響します。
最新動向・事例
AIモードの日本導入を受けて、業界側の反応や実例を把握しておくことは重要です。報道ベースでは、Faber Companyが緊急ウェビナー(2025年9月19日開催予定)を発表し、多くのコンサルやSEO事業者が短期間で対応策を議論しています。また、読売新聞系の報道では検索シェア低下への危機感も指摘されており、メディア運営者はトラフィック減少リスクを真剣に検討しています。
実際の初期ケーススタディとしては、以下のような動きが観察されています。
- eコマース:製品ページの短い要約とスペック表がAI回答に引用され、購入への導線("商品ページへ"リンク)を維持している例。
- B2B:ホワイトペーパーの要約を整備することで、AIモードの回答内で引用され問い合わせが増加した事例。
- メディア:長文記事の"要点まとめ"を作成しておくことで、AIによる要約表示が発生し、ブランド露出は維持されたが直帰率の変化を招いた例。
これらはまだ初期段階のエビデンスですが、共通する成功因子は"明確な要約と一次情報の提示"です。
マルチモーダル活用事例
画像や音声を活用した事例も増えています。例えば飲食チェーンが料理写真に詳細なキャプションと調理情報を付与した結果、ユーザーが写真をアップロードして類似メニューの説明を求めた際にAIが自社情報を引用、来店促進につながったケースがあります。動画企業はトランスクリプトを整備することでAIモードの回答に引用されやすくなっています。
マルチモーダルのポイントは「機械が読み取りやすいメタ情報を付与すること」です。画像そのものだけでなく、説明テキスト、製品ID、時間コードなどを埋めることで引用可能性が高まります。
ゼロクリックとメディア戦略
AIモードの普及は"ゼロクリック"の増加を意味します。読売新聞系の報道でも指摘されたように、検索結果内で完結する情報提示はウェブサイトへのトラフィックを減らす可能性があります。しかし、これは必ずしも悪いことではありません。識別化された戦略を取ることで、AIによる事前情報提示をリード獲得やブランド強化に転換できます。
具体策としては、AIが提示する要約内に"詳細はここ"と誘導する短いCTA(コールトゥアクション)を構造化データや冒頭要約に組み込む方法があります。さらに、ホワイトペーパーやツール、無料診断など"価値の高い次のアクション"をサイト上に用意しておくことで、AI経由のユーザーをコンバージョンへ繋げやすくなります。
課題と解決策
AIモード導入で直面する主な課題と、それに対する実務的な解決策をまとめます。
課題1: ゼロクリックによるトラフィック低下 解決策: サイト上にAIが参照する価値ある"次のステップ"(無料ツール、ダウンロード、会員登録)を設置し、要約内に誘導可能な要素を用意する。
課題2: 誤情報や出典不明瞭な引用 解決策: 構造化データで出典情報を明示し、一次ソースのURLや公開日、著者を明記する。ファクトチェックのためのメタタグ運用も検討する。
課題3: 多言語・文化適応の問題 解決策: 日本語コンテンツのローカライズ品質を高め、用語集や業界固有表現の統一を行う。翻訳コンテンツは必ずネイティブ校正を実施する。
課題4: 技術的対応リソース不足 解決策: 優先度の高いページから段階的にAIOを実装。外部パートナーやツールを活用し、内部での知見蓄積を進める。
これらの施策を組み合わせることで、AIモード時代におけるリスクを低減し、機会を最大化できます。
よくある質問
Q: GoogleのAIモードはいつ日本で開始されましたか?
A: Googleは日本語を含む複数言語でAIモードの提供を開始し、報道では2025年9月9日に日本版の提供が始まったとされています。導入に伴う公式情報はGoogleのアナウンスを確認してください。
Q: AIモードはどのような入力に対応していますか?
A: AIモードはテキスト検索に加えて、音声や画像入力をサポートするマルチモーダル機能を備えています。スマホからの音声入力や画像アップロードでの応答が可能です。
Q: 企業サイトがAIモードで引用されるには何が必要ですか?
A: 基本は構造化データ(FAQ、Article、Product等)の実装、記事冒頭の要約、出典と更新日の明示、画像のaltやトランスクリプト整備です。これらが引用シグナルになります。
Q: ゼロクリック時代にトラフィックを守る方法は?
A: サイト内で価値の高い次アクションを用意することが重要です。無料ツール、ホワイトペーパー、会員限定コンテンツを設置し、AI要約からの誘導を設計してください。
Q: AIモードでの誤情報対策はどうすればいいですか?
A: 出典を明示し、一次ソースへリンクすることが最も有効です。公開日や著者情報を明示し、可能なら信頼できるデータや研究を引用して裏取りを行ってください。
Q: SEOチームは何を最優先すべきですか?
A: 優先順位は、重要ページの要約整備、構造化データ導入、画像・音声メタデータの付与、そしてモニタリング体制の構築です。まずは上位30ページから着手しましょう。
Q: AIモードの表示を個別にトラッキングできますか?
A: 公式の分離指標はまだ整備途上ですが、Search ConsoleやGA4でクエリ分類し、AI関連のトラフィック変化を定期的に分析することで間接的に把握可能です。専用ツールの導入も検討してください。
Q: 中小企業でもAIモード対策は可能ですか?
A: 可能です。最初は最重要ページを3〜10件選び、要約と構造化データを実装するだけでも効果が出ます。段階的にリソースを割り当てるのが現実的です。
まとめ
GoogleのAIモード日本開始は検索体験とデジタルマーケティングの大きな転換点です。企業は従来のクリック重視指標から、AIに引用される信頼性と価値提供にKPIを転換する必要があります。実務的には、構造化データの実装、記事冒頭の要約化、出典・著者情報の明示、画像・音声メタデータの整備が最優先事項です。これらは短期間で実施可能であり、AIモード下での可視化とブランド価値維持に直結します。
また、ゼロクリック化への恐れをそのまま放置せず、AI表示を逆手に取ってリード獲得や有料サービスへの導線を設計することが重要です。具体的には無料ツールやホワイトペーパー、限定コンテンツを用意し、AIが提示する要約から自然に遷移できる設計を行ってください。
最後に、AIモードは技術と運用の両面で進化します。定期的なモニタリングとA/Bテスト、外部の動向把握(例: Faber Companyのウェビナー等)を継続し、変化に柔軟に対応する体制を作ることが成功の鍵です。今すぐ実行できる第一歩は、最重要ページの要約作成とJSON-LDによるFAQ/Articleマークアップの実装です。これによりAIモード時代の検索流入を取り込み、ビジネス成果へつなげてください。
📚 関連情報
📱 関連ショート動画
この記事の内容をショート動画で解説
著者について

原田賢治
代表取締役・AI技術責任者
Mike King理論に基づくレリバンスエンジニアリング専門家。生成AI検索最適化、ChatGPT・Perplexity対応のGEO実装、企業向けAI研修を手がける。 15年以上のAI・システム開発経験を持ち、全国で企業のDX・AI活用、退職代行サービスを支援。